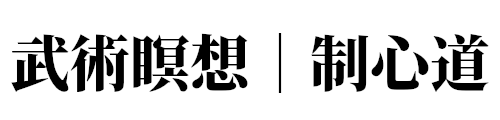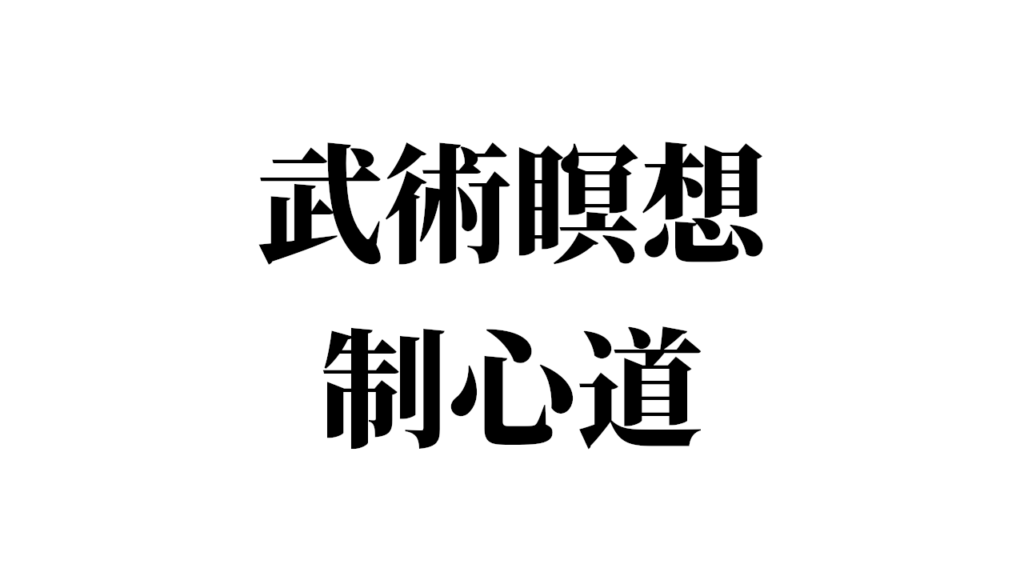パワハラ上司とすぐ辞める若手はどちらが悪いか
職場でしばしば問題となる「パワハラ上司」と「すぐに辞める若手社員」。この二つの現象は、現代の職場における世代間ギャップを象徴する対立構造として語られることが多い。しかし、この問いに対して安易に白黒をつけることは、問題の本質を見誤ることになりかねない。
まず理解すべきは、パワーハラスメントは明確に違法行為であり、人権侵害だということだ。大声で怒鳴る、人格を否定する、無理な要求を押し付ける、無視や仲間外れにするといった行為は、どのような理由があろうとも正当化されない。「昔はこれが当たり前だった」「自分もこうやって育てられた」という言い訳は通用しない。時代が変われば価値観も変わる。かつて許容されていた指導方法が、今では暴力や虐待と認識されるのは当然の道理である。
一方で、若手社員がすぐに退職することを安易に批判することもできない。彼らが辞める理由は多岐にわたる。理不尽な扱いを受けている、成長の機会がない、労働環境が劣悪である、約束された条件と実態が違う。こうした正当な理由で退職を選ぶことは、自己防衛であり、賢明な判断ですらある。「石の上にも三年」という言葉は、その三年間に得られるものがある場合にのみ意味を持つ。何も学べず、ただ消耗するだけの環境に留まることは美徳ではない。
ただし、すべての若手の早期退職が正当化されるわけでもない。些細な注意を受けただけで「パワハラだ」と主張したり、自分の努力不足を棚に上げて環境のせいにしたり、最初から腰を据えて働く気がないまま入社したりするケースも存在する。こうした姿勢は、本人のキャリア形成にとってマイナスになるだけでなく、組織にも無用な混乱をもたらす。
問題の核心は、「どちらが悪いか」という二項対立の構図そのものにある。多くの場合、職場の問題は複合的な要因によって生じている。パワハラ上司が生まれる背景には、過度なプレッシャー、マネジメント教育の不足、組織文化の歪みがある。若手が定着しない職場には、採用のミスマッチ、育成体制の不備、コミュニケーション不全が存在する。
本来問われるべきは、組織として健全な職場環境を構築できているかどうかだ。上司には適切な指導方法を学ぶ機会が与えられているか。若手には成長を実感できる仕事とフィードバックが提供されているか。世代間の価値観の違いを埋めるための対話の場があるか。こうした構造的な問題に目を向けずに、個人の責任論に終始しても解決には至らない。
結局のところ、パワハラをする上司は間違っている。それは議論の余地がない。同時に、すぐに辞める若手を一概に批判することもできない。彼らの多くは、自分の人生を守るために合理的な選択をしているに過ぎない。この問題に真摯に向き合うなら、個人の善悪を裁くのではなく、なぜそのような事態が生じるのかという組織の在り方こそを問い直すべきである。
=======
本物の武術に興味がある方はご参加ください
↓ ↓ ↓
LINEオープンチャット
「秘伝実践会セミナー告知連絡用」
著作物紹介:
※kindle unlimited にご登録中の方は全て無料で読めます。(未登録の方は30日間無料体験を使えば無料で読めます)
「リーダーのための瞑想トレーニング」
「あなたの知らない非常識な幸せの法則」
「超速化時代の冒険:AIライティングと武術気功の叡智」
「AIライティング最速出版術」
空手家との組手や演武などの動画は下記サイトでご覧いただけます。
(武術気功健康教室|大阪府四條畷市)