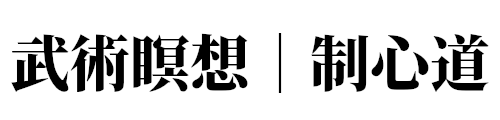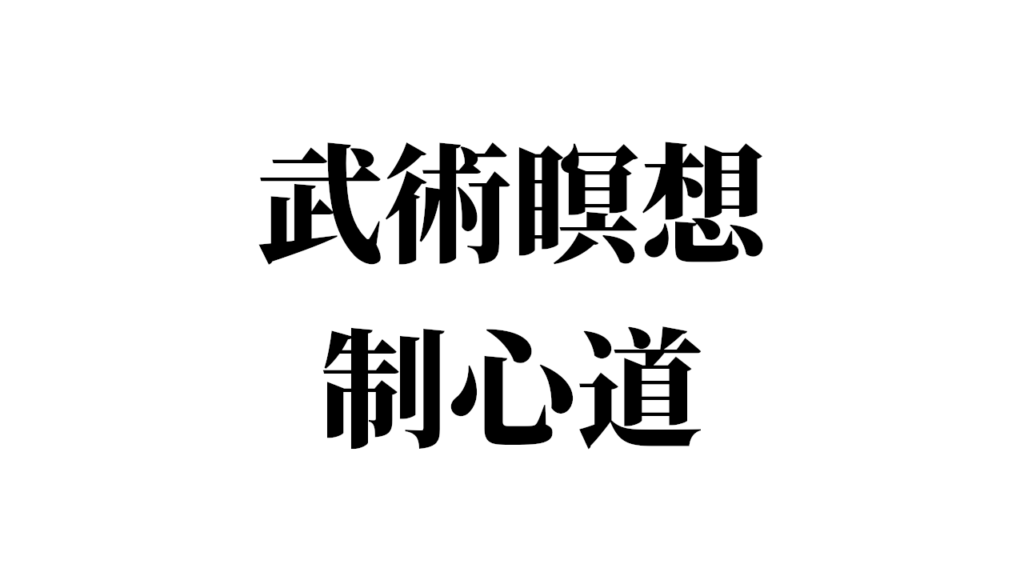力は抜いて気を入れる
武術においては力より「気」を重視する。この一見オカルトチックな表現は、実は身体操作と精神統一の本質を表し、極めて汎用性の高い深遠な智慧である。
我々は何かを成し遂げようとする時、つい力んでしまう傾向がある。重いものを持ち上げる時であればそれでいい。だが難しい問題に取り組む時、緊張する場面に臨む時、無意識のうちに全身に無駄な力を込めてしまう。このような力みは往々にして逆効果をもたらす。筋肉が硬直すると動きは鈍くなり、呼吸は浅くなり、集中力も散漫になってしまう。
「力を抜く」とは、不要な筋緊張を解き放つことである。肩の力を抜き、顎の力を緩め、全身をリラックスした状態に保つ。これは決して気力を失うことや、だらけることを意味するのではない。むしろ、身体を最も効率的に動かすための準備である。力が抜けた状態では、筋肉は柔軟性を保ち、関節は自然な可動域を維持し、血流も良好になる。このような身体状態こそが、本来の力を発揮するための土台となる。
一方で「気を入れる」とは、精神の集中と意識の統一を指す。気とは東洋思想における生命エネルギーの概念であり、意識や注意力、精神力といったものに近い。気を入れるということは、散漫になりがちな意識を一点に集中し、目的に向かって精神を統一することである。これは単なる力任せとは全く異なる、内面からの充実した力、感覚の研磨といえる。
この二つの要素が組み合わさることで、人は驚くべき能力を発揮することができる。書道における筆運びを考えてみよう。筆を握る手に力が入りすぎていては、流れるような線は描けない。しかし、ただ力を抜いただけでは、筆はぶれてしまい、意図した線を描くことはできない。大切なのは、手や腕の力を抜きながらも、精神を集中し、描こうとする文字に気を込めることである。
武道においても同様である。剣道の素振りでは、握り拳に力を込めすぎると竹刀の動きは重くなり、相手の動きに対応することが困難になる。しかし、気を抜いてしまえば、竹刀は軽くなりすぎて威力を失う。理想的な状態は、握りは柔らかく保ちながらも、精神は研ぎ澄まし、一瞬の機会を逃さない集中力を維持することだ。
日常生活においても、この原理は応用できる。プレゼンテーションを行う際、緊張のあまり肩や首に力が入ってしまうと、声は上ずり、身振りは硬くなってしまう。しかし、深呼吸をして身体の力を抜き、同時に伝えたいメッセージに気を込めることで、自然で説得力のある話し方ができるようになる。
スポーツの世界でも、この考え方は重要だ。ゴルフのスイングにおいて、力いっぱい振ろうとすると、かえってボールは思った方向に飛ばない。大切なのは、グリップの力を抜き、身体全体をリラックスさせながらも、ボールを正確に捉えようとする集中力を保つことだろう。
この「力は抜いて気を入れる」という状態は、一朝一夕に身につくものではない。長年の修練を通じて、徐々に体得していくものだ。最初は意識的に力を抜こうとしても、すぐに元の力んだ状態に戻ってしまうことが多い。また、気を入れることも、単に「頑張ろう」と思うだけでは不十分だ。深い集中状態に入るためには、呼吸法や瞑想といった具体的な技法を学ぶ必要がある。
現代社会はストレスに満ちており、多くの人が常に緊張状態にある。そのような環境だからこそ、「力は抜いて気を入れる」という古来の智慧は、より一層の価値を持つ。この状態を身につけることで、あなたはより効率的に行動し、より深く集中し、より豊かな人生を送ることができるはずだ。
真の力とは、筋力だけでなく、心の力、精神の力を含んだ総合的なものといえる。そして、その力を最大限に発揮するためには、まず不要な力みを捨て、純粋な意識の集中を培うことが不可欠なのである。
=======
本物の武術に興味がある方はご参加ください
↓ ↓ ↓
LINEオープンチャット
「秘伝実践会セミナー告知連絡用」
著作物紹介:
※kindle unlimited にご登録中の方は全て無料で読めます。(未登録の方は30日間無料体験を使えば無料で読めます)
「リーダーのための瞑想トレーニング」
「あなたの知らない非常識な幸せの法則」
「超速化時代の冒険:AIライティングと武術気功の叡智」
「AIライティング最速出版術」
空手家との組手や演武などの動画は下記サイトでご覧いただけます。
(武術気功健康教室|大阪府四條畷市)