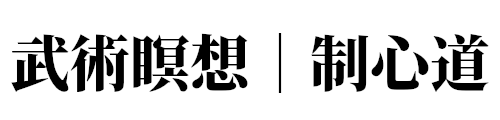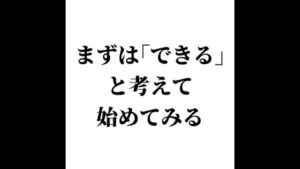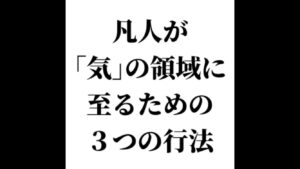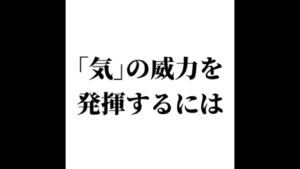制心道
まずは「できる」と考えて始めてみる
何でも案外「やればできる」 人生において新しいことに挑戦する時、多くの人は「自分にはできないのではないか」という不安や恐れを感じる。しかし、制心道では、まずは「できる」という前提で物事を始めることを重視している。これは単 […]
あなたの心身があなたの神様
「気」と身体(命の体現)は、まさに神聖なる存在だ。古来より東洋の叡智は、人体を小宇宙と捉え、その中に無限の可能性が秘められていることを説いてきた。道家思想では、この身体を「気」という生命エネルギーの源として大切にし、それ […]
次世代リーダーは「気」を学ぶべき理由
現代のビジネス環境は急速に変化し、複雑化が加速している。このような状況下で、次世代のリーダーには従来とは異なる能力や視点が求められてきている。 その中で、古来から東洋の哲学や武術で重要視されてきた「気」の概念を学ぶことが […]
あなたが途轍もなく尊い理由
人生の旅路において、あなたは常に最善を尽くす意識を持ち続けている。それは単なる理想ではなく、日々の生活の中で実践しようと努力し、創意工夫を重ねている姿勢だ。この姿勢こそが、あなたの尊さを物語る一つの証である。 最善を尽く […]
凡人が「気」の領域に至るための3つの行法
気の領域に至ることは、多くの人にとって神秘的で遠い存在に感じられるかもしれない。しかし、凡人であっても適切な行法を実践することで、気の領域に近づくことは可能だ。ここでは、そのための3つの重要な行法について解説しよう。 ま […]
「気」の威力を発揮するには
「気」の概念は、古来より東洋の武術や哲学において重要な位置を占めてきた。 これは単なる物理的な力や技術だけでなく、精神的な要素が人間の能力を大きく左右するという深い洞察に基づいている。 「気」とは、生命エネルギーや宇宙の […]
自分の「気」と身体に投資する
絶対に失敗しない投資 現代社会において、多くの人々は外的な成功や物質的な豊かさを追求することに夢中になっている。しかし、本当の幸福と充実した人生は、自分自身の内なる力を育むことから始まる。その中でも特に重要なのが、自分の […]