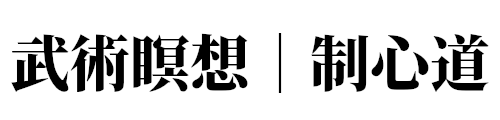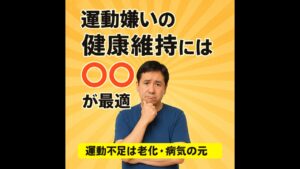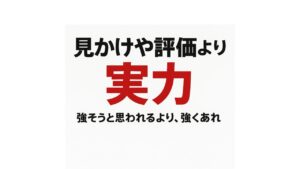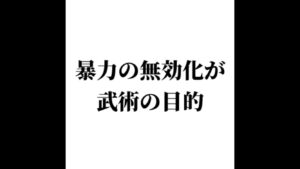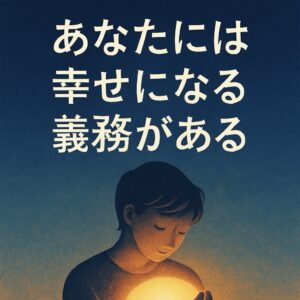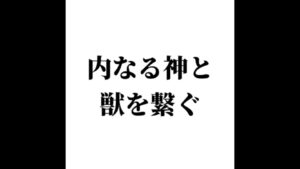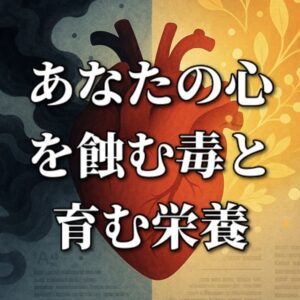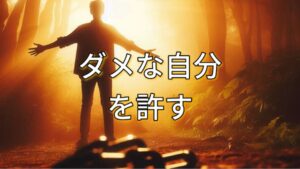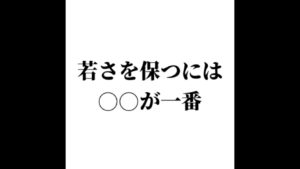制心道
運動嫌いの健康維持には〇〇が最適な理由
運動不足は老化・病気の元── 現代社会において健康維持の重要性は広く認識されている。だが運動を苦手とする人々にとって日常的な身体活動を取り入れることは容易ではない。特に激しいランニングやジムでのトレーニングといった従来型 […]
見かけや評価より実力
強そうと思われるより、強くあれ── 社会では往々にして外見や他者からの評価が重視される傾向にあるが、真に価値があるのは実力そのものだ。外見の良さや周囲からの高評価は一時的な利益をもたらすかもしれないが、長期的な成功と充実 […]
セックス、スポーツ、スクリーン
「3S愚民化政策」をご存知だろうか。 3S政策 現代社会において、大衆を管理しやすくするために意図的に用いられているとされ、日本人に対しては戦後GHQによって仕掛けられた。 先述のWikiによれば、以下の事実が確認されて […]
暴力の無効化が武術の目的
武術の真髄は、攻撃や破壊ではない。それはより深遠な目的に根ざしている。真の武術は暴力を完全に無効化する。伝統的な武術は単に敵を倒すための技法の集積ではなく、むしろ争いそのものを避け、必要な場合にのみ最小限の力で対応すると […]
あなたには幸せになる義務がある
権利ではなく、義務── 人は皆、幸せになる義務を持っている。この一見奇妙な主張を伝えたい。我々は普段、義務というと重荷や制約を連想しがちだが、幸せになる義務とは何を意味するのだろうか。 幸せとは本来、自分自身のためのもの […]
あなたの心を蝕む毒と育む栄養
最悪、死ぬより不幸になる── 我々は日々、食事について考える時間を持つ。身体に良い食品を選び、栄養バランスを整え、時には身体に悪いと分かっていながらも味や満足感を求めて不健康な食品を口にすることもある。しかし、心の健康に […]
若さを保つには◯◯が一番
もしあなたが「若返りたい」「若さを保ちたい」と少しでも願うなら、この記事は役立つかもしれない。 武術の練習は古来より健康と若さを保つための優れた方法として知られてきた。心身の調和を重視する東洋の武術は、単なる戦いの技術で […]
運を良くする習慣、悪くする習慣
あなたは日々の行動や考え方によって、自らの運命を少しずつ形作っている。あなたが何気なく続けている習慣の中には、知らず知らずのうちに運気を高めているものもあれば、逆に運を遠ざけてしまうものもある。 運を良くする習慣は、まず […]